※Claude 3.7 Sonnetにて出力。
人口危機に立ち向かう隣国:韓国と日本の共通課題
少子高齢化は東アジア全体が直面する深刻な課題となっていますが、特に韓国の状況は急速に悪化しています。2023年の韓国の合計特殊出生率は0.72と、OECD諸国の中で最低水準に達しました。日本の1.3を大きく下回るこの数字は、韓国社会に大きな衝撃を与えています。両国とも人口減少による労働力不足という共通の課題に直面していますが、その対策には類似点と相違点があります。外国人労働者の受け入れという選択肢において、韓国と日本はどのような政策を展開してきたのでしょうか。今回は、両国の外国人労働政策を比較しながら、その特徴や課題、そして日本が韓国から学べる点について探っていきます。
韓国の外国人労働政策の変遷と現状
韓国の外国人労働者受け入れ制度は1990年代に始まり、2004年に「雇用許可制度(Employment Permit System: EPS)」として確立されました。この制度は、主に中小企業の労働力不足を補うために導入され、外国人労働者に最長4年10カ月の就労を認めるものです。
雇用許可制度の特徴は、政府が主導して外国人労働者を選抜し、企業とのマッチングを行う点にあります。韓国語能力試験(TOPIK)の合格を条件とするなど、言語能力も重視しています。対象国は現在16カ国で、主にベトナム、フィリピン、インドネシアなどアジア諸国からの受け入れが中心となっています。
近年では特に製造業、建設業、農業・漁業といった人手不足が深刻な分野での外国人労働者の需要が高まっています。2023年時点で約27万人の外国人労働者がEPS制度のもとで韓国で働いていますが、コロナ禍による入国制限の影響で一時的に減少した後、再び増加傾向にあります。
また、韓国では2010年以降、より高度な技術を持つ外国人材を対象とした「ポイント制ビザ制度」も導入されており、学歴や韓国語能力、職歴などに応じてポイントを付与し、一定以上のポイントを獲得した外国人に就労ビザを発給する制度も運用されています。
日本との制度的比較:類似点と相違点
日本の外国人労働者受け入れ制度である「技能実習制度」と「特定技能制度」は、韓国のEPS制度と目的において類似していますが、運用方法に大きな違いがあります。
技能実習制度は、国際貢献の名目で外国人に技能を習得させるという建前がありますが、実質的には労働力不足を補う役割を果たしてきました。しかし、監理団体や送り出し機関を通じた複雑な仲介構造が、高額な手数料や不正行為の温床となりやすいという問題があります。
対照的に、韓国のEPS制度は政府が直接管理する形態をとっており、民間の仲介業者を排除することで不正行為やコスト増を防ぐ工夫がされています。また、韓国では労働者の権利保護の観点から、最低賃金や労働条件について日本よりも厳格な適用がなされる傾向があります。
業種別に見ると、日本の特定技能制度は14の特定産業で外国人労働者を受け入れていますが、韓国のEPS制度では製造業に加え、農業・漁業分野での受け入れにも力を入れている点が特徴的です。また、韓国では建設業での外国人労働者の活用が進んでいる一方、日本では建設業における外国人労働者の活用はまだ限定的な面があります。
韓国の外国人労働政策の効果と課題
韓国のEPS制度は、透明性が高く政府主導型の仕組みとして一定の成果を上げていますが、課題も少なくありません。
まず、効果としては、中小企業の人手不足の緩和に貢献している点が挙げられます。製造業を中心に、外国人労働者なしでは操業が難しい企業も多くあります。また、政府主導の選抜・マッチングにより、仲介業者による搾取や不正が比較的少ないという評価もあります。
しかし、課題も多く存在します。最大の問題は、就労期間の上限である4年10カ月を超えると帰国しなければならない点です。これにより、熟練した労働者が継続して働けないという非効率が生じています。また、雇用主を変更する際の制限が厳しく、労働者の権利が制約される側面もあります。
さらに、低賃金労働への依存が高まることで、産業の構造改革や生産性向上への取り組みが遅れるリスクも指摘されています。韓国国内では、「外国人労働者の増加が賃金抑制につながる」という批判もあり、労働組合からの反発も少なくありません。
最近では、不法滞在者の増加も深刻な問題となっています。2023年の統計によると、韓国内の不法滞在者は約40万人に達しており、これはEPS制度で正規に就労する外国人労働者数を上回る規模となっています。
日韓両国の課題:待遇改善と社会統合の必要性
日韓両国に共通する課題として、外国人労働者の待遇改善と社会統合の問題があります。
韓国では、外国人労働者に対する差別や人権侵害の事例が報告されており、日本の技能実習生が直面する問題と類似した状況が見られます。労働環境の改善や権利保護の強化は、両国にとって重要な課題です。
また、長期的な人口減少対策としては、単なる労働力確保を超えた社会統合の視点が必要です。韓国では近年、多文化家族支援センターの設置など、外国人の社会統合を促進する取り組みが進められていますが、日常生活における差別や偏見の解消には至っていません。
日本でも「特定技能2号」のように、より長期的な在留を認める制度が始まっていますが、家族帯同や永住への道筋が明確でないなど、真の社会統合に向けた課題は残されています。世界的な人材獲得競争が激化する中、外国人労働者を一時的な「ゲストワーカー」ではなく、社会の一員として受け入れる発想の転換が両国に求められているといえるでしょう。
韓国の新たな取り組み:デジタル人材の確保と海外進出支援
韓国政府は2022年以降、外国人労働者政策について新たなアプローチを模索しています。特に注目されるのが、高度外国人材、特にデジタル分野の専門家の積極的な誘致です。
「K-デジタルビザ」と呼ばれる新制度では、IT・デジタル分野の人材に対して優遇措置を講じ、スタートアップ企業との連携も促進しています。この分野では日本よりも積極的な姿勢を見せており、韓国の産業構造の高度化を図る狙いが見て取れます。
また、韓国企業の海外進出支援と連動した人材確保の取り組みも特徴的です。韓国企業がベトナムやインドネシアなどに進出する際、現地での人材育成と韓国での就労をセットで考える「循環型人材育成」の発想が浸透しつつあります。
さらに、地方自治体レベルでの取り組みも活発化しており、外国人労働者の受け入れと地域活性化を結びつける政策が各地で展開されています。例えば、忠清南道では外国人労働者向けの専用住宅を整備し、地域社会との交流促進を図るプロジェクトが進行中です。
日本が韓国から学べる点:統計データから見た示唆
韓国のEPS制度と日本の技能実習・特定技能制度の運用実績を比較すると、いくつかの興味深い点が浮かび上がります。
まず、政府主導の選抜・マッチングシステムの効率性です。韓国のEPS制度では、外国人労働者の離職率が日本よりも低い傾向にあります。2022年の統計によると、韓国のEPS制度下での離職率は約15%であるのに対し、日本の技能実習生の離職率は約25%と報告されています。このギャップは、マッチングの質と関連している可能性があります。
また、言語教育の重視も参考になる点です。韓国では入国前の韓国語教育に力を入れており、社会統合の基礎として言語能力を重視しています。日本語能力が必ずしも重視されていない技能実習制度とは対照的です。
さらに、デジタル化の推進も注目点です。韓国では外国人労働者の管理システムがデジタル化されており、リアルタイムで労働環境や待遇をモニタリングできる仕組みが整備されつつあります。日本でも特定技能制度の運用において、こうしたデジタル技術の活用が検討される価値があるでしょう。
まとめ:持続可能な外国人労働政策に向けて
韓国と日本は、少子高齢化による人口減少という共通の課題に直面しており、外国人労働者の受け入れを重要な対策の一つとして位置づけています。両国の制度には類似点と相違点がありますが、いずれも完璧な解決策とは言えず、試行錯誤の段階にあります。
韓国のEPS制度からは、政府主導の透明性の高いマッチングシステムや、言語教育の重視といった点が参考になります。一方で、就労期間の制限や不法滞在者の増加など、韓国も深刻な課題を抱えています。
日本が今後、持続可能な外国人労働政策を構築していくためには、単なる労働力不足の穴埋めではなく、産業構造の高度化や生産性向上と連動した人材戦略が求められます。また、外国人労働者を「一時的な労働力」としてではなく、社会の一員として受け入れる包括的なアプローチも重要です。
人口減少は日韓両国にとって長期的な課題であり、外国人労働者政策もまた長期的な視点での設計が必要です。韓国の経験から学びつつ、日本の状況に適した独自の解決策を模索していくことが、今後の日本の外国人労働政策の発展につながるでしょう。グローバルな人材獲得競争が激化する中、魅力的な就労環境と社会統合の仕組みを整えることが、日本の持続的な発展のカギを握っています。


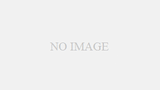
コメント